【PR】
離乳食が進んでくると、野菜だけでなくたんぱく質を積極的に取り入れたい時期がやってきます。その中でも「鶏ひき肉」は、やわらかくて消化がよく、離乳食に取り入れやすい食材のひとつです。
しかし「いつから与えられる?」「脂肪分の少ない部位は?」「そぼろにしても大丈夫?」など、与え方や調理法に悩むママやパパも多いでしょう。
この記事では、鶏ひき肉を離乳食に取り入れる時期の目安、下ごしらえの方法、月齢別のおすすめレシピを詳しく解説します。
さらに、鉄分補給の工夫や注意点、よくある質問も取り上げ、赤ちゃんの食事に安心して活用できるようサポートします。
鶏ひき肉はいつから与えられる?
鶏ひき肉は離乳食中期(7〜8ヶ月頃)から与えることができます。離乳食初期にはまだ消化機能が未発達なため、魚や豆腐からたんぱく質を始めるのが一般的ですが、中期以降は鶏ひき肉を少量から試せるようになります。
中期(7〜8ヶ月):ゆでて細かくほぐし、なめらかにしたものを少量から
後期(9〜11ヶ月):鶏団子やそぼろにして与える
完了期(12〜18ヶ月):炒め物やおやき、オムレツなどに活用可能
鶏ひき肉の栄養
鶏ひき肉は赤ちゃんの成長に必要なたんぱく質をはじめ、以下の栄養素を含みます。たんぱく質:筋肉や臓器の発達に欠かせない
ビタミンB群:代謝をサポートし、エネルギーに変える
鉄分:赤血球の材料となる(ただし含有量は多くないため補助が必要)
脂肪分が少ない「むね肉」や「ささみ」のひき肉が離乳食には最適です。
下ごしらえの方法
鶏ひき肉を安全に離乳食に使うためには、必ず以下の下ごしらえを行いましょう。・沸騰したお湯でしっかりゆでる
・アクを丁寧に取り除く
・ザルにあげて湯切りをする
・月齢に合わせて細かく刻んだり、ペースト状にする
鶏ひき肉は生の状態で菌が繁殖しやすいため、必ず中心まで加熱することが大切です。
月齢別のおすすめレシピ
中期(7〜8ヶ月)
・鶏そぼろあんかけがゆ・鶏ひき肉入り野菜スープ
後期(9〜11ヶ月)
・鶏団子の煮物・鶏ひき肉と豆腐のおやき
・鶏そぼろ入りうどん
完了期(12〜18ヶ月)
・鶏ひき肉入りオムレツ・鶏そぼろ丼(薄味で)
・鶏ひき肉と野菜の炒め物
与えるときの注意点
・必ず中心まで加熱する:加熱不足は食中毒のリスク・脂肪分に注意:皮付きやもも肉のひき肉は脂質が多いため避ける
・保存方法:使い切れない場合は冷凍保存し、1週間以内に消費
・アレルギー:鶏肉アレルギーは少ないですが、初めての場合は少量から試す
鉄分不足への対策はサプリメントで
鶏ひき肉は良質なたんぱく質源ですが、鉄分は不足しがちです。離乳食中期からは鉄分不足に注意が必要です。
にこにこ鉄分は無味無臭の粉末タイプで、おかゆやスープ、オムレツに混ぜるだけで鉄分を効率的に補えます。
1包あたり鉄分4.5mgを配合し、さらに吸収をサポートするビタミンCや葉酸も同時に摂れるのが特長。
砂糖・着色料・保存料は一切不使用で、国内のGMP認定工場で製造・検査を徹底しているため、毎日安心して続けられます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 鶏ひき肉はそのまま炒めてもいい?
A. 離乳食では炒めるよりも茹でて脂を落とすのが基本です。Q2. 鶏ひき肉の冷凍保存は可能?
A. 調理後に小分けして冷凍可能です。1週間を目安に使い切りましょう。Q3. 鶏団子は何ヶ月から?
A. 後期(9〜11ヶ月)から少量であればOKです。やわらかく仕上げましょう。Q4. ひき肉を嫌がるときは?
A. 野菜や豆腐と混ぜると食べやすくなります。Q5. コンビニの鶏そぼろは使える?
A. 調味料や塩分が多いため離乳食には不向きです。必ず手作りで用意してください。まとめ
鶏ひき肉は離乳食中期から使える便利なたんぱく質源です。脂肪分の少ない部位を選び、必ず中心まで加熱してから与えることが大切です。
月齢に合わせたレシピでバリエーションを広げれば、赤ちゃんの食欲もアップ。鉄分不足が心配な時期にはにこにこ鉄分などのサプリメントを取り入れ、安心して栄養バランスを整えましょう。


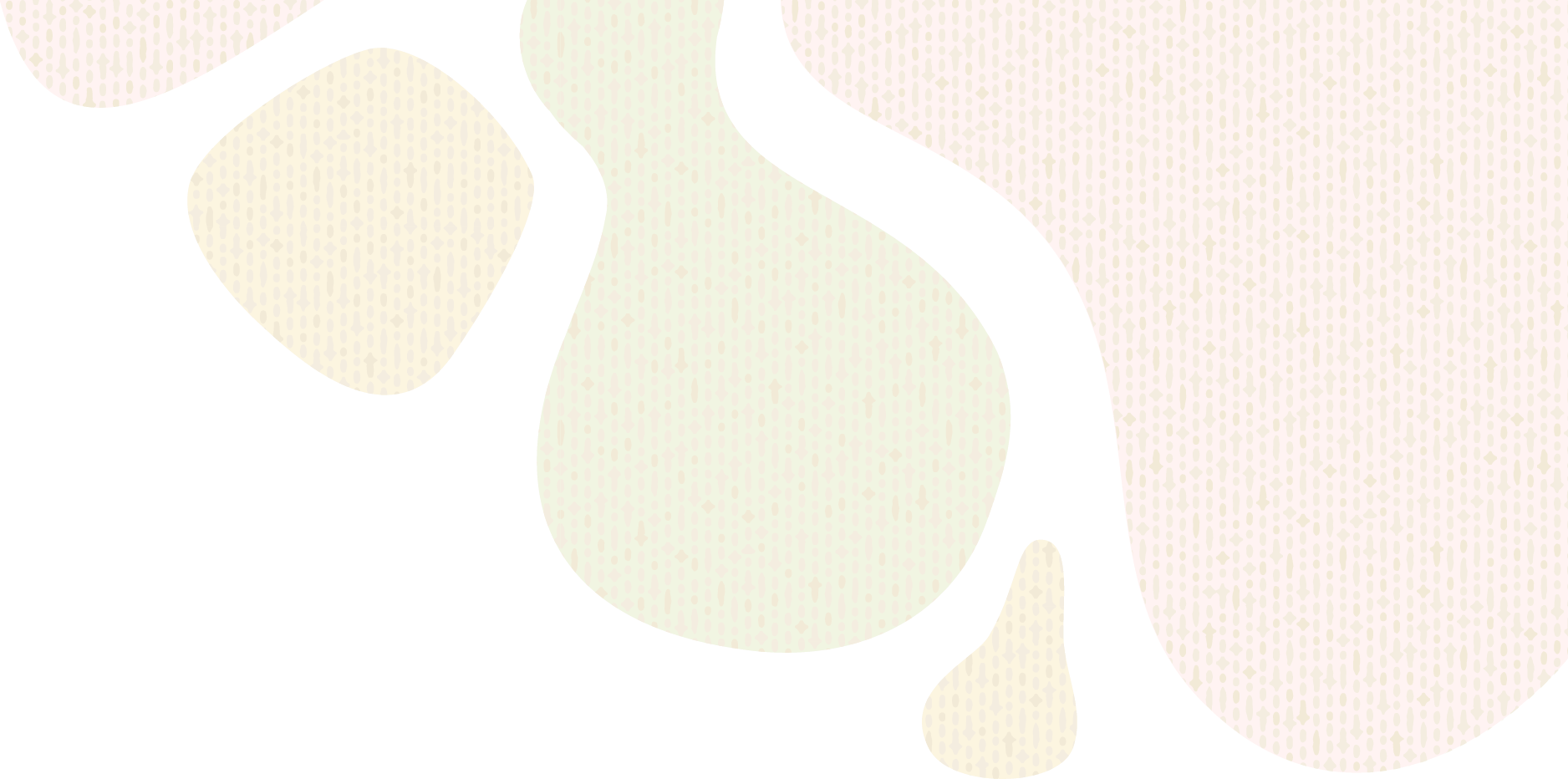











 にこにこ鉄分特設サイト
にこにこ鉄分特設サイト





