【PR】
ツナ缶は手軽に使えて大人の料理でも大活躍する食材です。ところが、「赤ちゃんの離乳食にツナを使っても大丈夫?」「油漬けと水煮の違いは?」「与えるときに塩分や油分は心配ない?」など、疑問を持つママやパパも多いでしょう。
実際、ツナは手に入りやすく便利な一方で、選び方や下ごしらえを間違えると塩分や油分が赤ちゃんに負担となることもあります。
この記事では、ツナを離乳食に取り入れる時期の目安や安全な選び方、下ごしらえのポイント、月齢別の与え方やおすすめレシピを詳しく解説します。
さらに、ツナだけでは不足しやすい鉄分を補う工夫についても紹介し、赤ちゃんの栄養バランスをサポートします。
ツナは離乳食にいつから使える?
ツナは離乳食後期(生後9〜11ヶ月頃)から与えられる食材です。魚類の中でも食べやすく調理が簡単ですが、ツナ缶には塩分や油分が含まれるため、初期や中期には適していません。
初期(5〜6ヶ月)
ツナはまだ与えない中期(7〜8ヶ月)
消化機能が未発達なためツナは控える後期(9〜11ヶ月)
水煮缶を湯通しして使用すれば少量からOK完了期(12〜18ヶ月)
レシピの幅を広げて活用可能ツナ缶の選び方
赤ちゃん用にツナを選ぶときは、以下のポイントを意識しましょう。水煮タイプを選ぶ
油漬けは油分が多く、消化に負担をかけるため離乳食には不向きです。食塩無添加タイプ
塩分は赤ちゃんにとって負担になるため、無添加の水煮缶がベストです。国産・安全性の高い製品
できるだけ添加物の少ないものを選びましょう。下ごしらえの方法
ツナ缶を使うときは、必ず湯通しして余分な塩分や油分を取り除きます。・缶を開けてザルにあける
・熱湯を回しかけて油や塩分を落とす
・赤ちゃんの月齢に合わせて細かくほぐす
これで離乳食でも安心して使えます。
月齢別のツナの与え方
後期(9〜11ヶ月)
・湯通ししたツナをおかゆやスープに少量混ぜる・野菜と合わせて煮ると食べやすい
・最初は小さじ1からスタート
完了期(12〜18ヶ月)
・ツナサンド(パンがゆに混ぜる)・ツナ入りおやき
・ツナと野菜の炒め煮
・ツナ入りオムレツ
完了期は食べられる種類も増え、ツナを使ったアレンジの幅も広がります。
ツナの栄養と注意点
ツナはたんぱく質が豊富で、DHAやEPAなどの必須脂肪酸も含まれています。ただし注意点もあります。
・塩分/油分:缶詰の種類によっては多く含まれるため、必ず湯通しをする。
・水銀リスク:マグロ類の大型魚を原料とするツナは水銀を含む可能性があるが、少量なら問題なし。与えすぎは避ける。
・保存性:缶を開けたら使い切る。保存する場合は冷凍で小分けに。
また、ツナは鉄分をあまり含まないため、離乳食全体で鉄分を意識する必要があります。
にこにこ鉄分で栄養バランスを整える
鉄分不足が気になる時期には、にこにこ鉄分を活用するのがおすすめです。無味無臭の粉末タイプなので、おかゆやスープに混ぜるだけで簡単に鉄分を補えます。
1包あたり鉄分4.5mgを配合し、さらに吸収を助けるビタミンCや葉酸も同時に摂取可能。
砂糖・着色料・保存料は一切使用しておらず、国内のGMP認定工場で製造・検査を徹底しているため、安心して続けられます。
よくある質問(FAQ)
Q1. ツナ缶はそのまま使える?
A. 塩分や油分が含まれているため、必ず湯通ししてから与えましょう。Q2. ツナフレークと普通のツナは違う?
A. 基本的に同じですが、商品によって油や塩分の量が異なるため成分表示を確認しましょう。Q3. 冷凍保存はできる?
A. 湯通しして小分けにし、冷凍保存可能です。1週間程度を目安に使い切りましょう。Q4. 水銀の影響は心配ない?
A. 離乳食で与える程度の少量なら問題ありません。ただし毎日大量に与えるのは避けましょう。Q5. ツナを食べて下痢をした場合は?
A. 消化に負担がかかった可能性があります。しばらく中止し、医師に相談してください。まとめ
ツナは離乳食後期(9〜11ヶ月頃)から使える便利な食材です。必ず水煮タイプを選び、湯通しして塩分・油分を取り除いてから与えることが大切です。
完了期にはレシピの幅が広がり、オムレツやおやきなどで楽しめます。


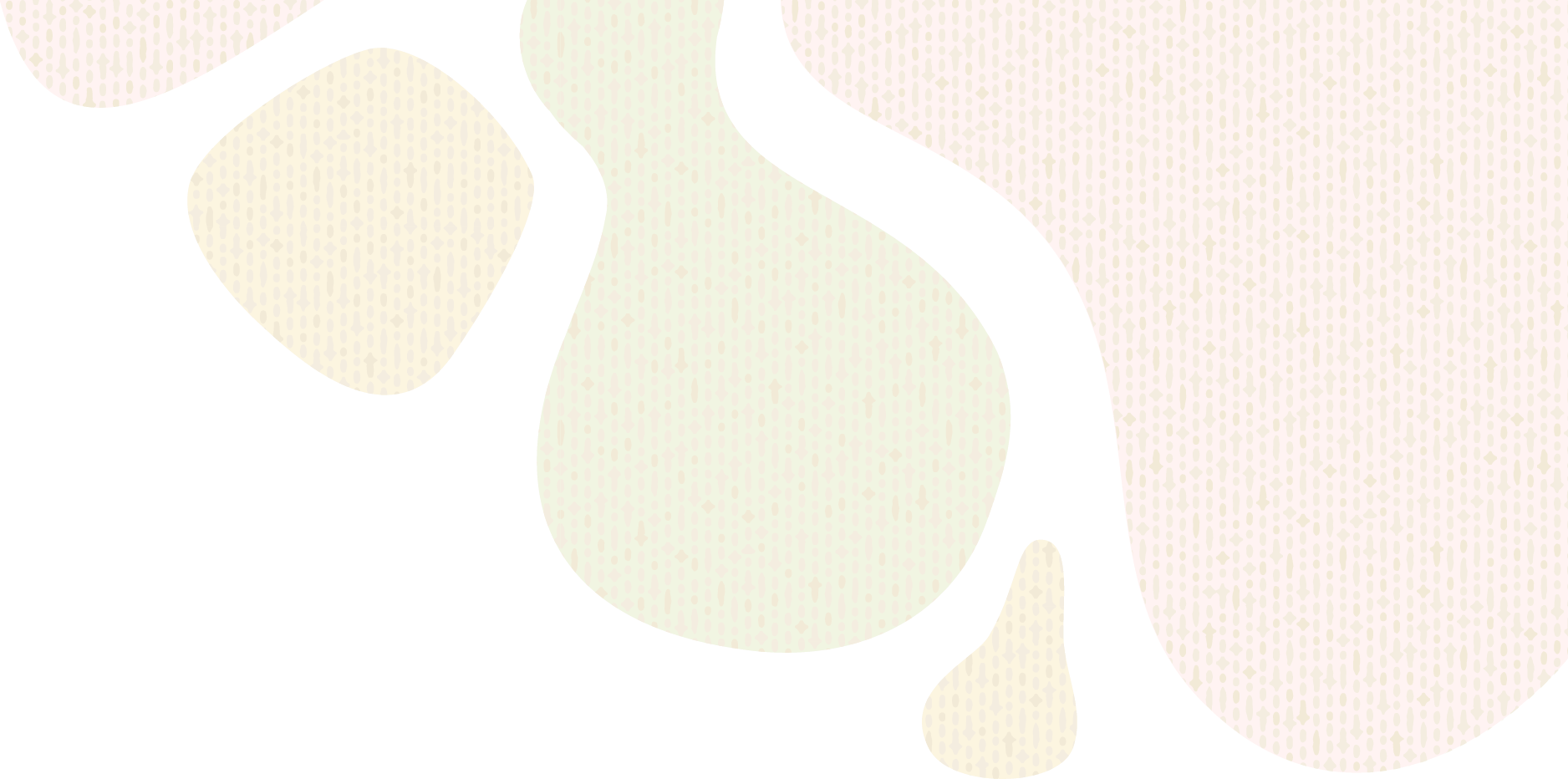











 にこにこ鉄分特設サイト
にこにこ鉄分特設サイト





