【PR】このページにはプロモーションが含まれています。
離乳食完了期とは?
離乳食の完了期は、生後12〜18カ月ごろを目安に開始します。今までは食べ物を歯茎でつぶして食べていた赤ちゃんが、歯茎で噛み切りながら食べられるようになってきます。
手づかみ食べだけでなくスプーンやフォークにも興味を示すようになるため、離乳食を与える際は完了期の赤ちゃんの成長に合わせた食べ物を用意してあげましょう。
<離乳食完了期を開始する目安>
・1日3回の食事のリズムがついている
・手づかみ食べができる
・口を上下左右に動かして食べられている
・食べ物を前歯でかじり取れる など
離乳食完了期(12〜18ヶ月)における離乳食の進め方
幼児食に移行するための最終ステップでもある完了期。必要な栄養素の大半を食事から補えるようになってきます。
大人とほとんど同じ食べ物を食べられるようになるので取り分けやすくはなりますが、まだかたい食べ物や味の濃い料理は向いていません。
離乳食完了期を進めるにあたって知っておきたい食材の大きさやかたさ、1回の目安量やスケジュールなど離乳食の進め方について管理栄養士が解説します。
完了期の食材の大きさとかたさ
離乳食完了期になると、上下の前歯8本が生えそろいます。歯茎で噛み切れるようになってくるため、比較的かたい食材でもしっかり加熱すれば食べられるようになります。
食材を角切りや千切りにする場合の大きさは、1cm程度にしてあげましょう。また手づかみ食べをするメニューは、スティック状や楕円形などかじり取りやすい形状にしてあげるといいですね。
完了期の赤ちゃんが食べるメニューは、ハンバーグや肉団子程度のかたさになるように作りましょう。大人の料理を再度やわらかく煮て、水を加えて薄味にしたものを与えるのもおすすめです。
完了期の1回の目安量
まだ大人に比べると1回で食べられる量は少ないため、1日3食の離乳食以外に1〜2回のおやつ(補食)を取り入れます。軟飯やごはんなどの炭水化物、肉や魚、大豆製品などのタンパク質、野菜や果物、海藻類などのビタミンやミネラルが補える食べ物を組み合わせましょう。
1回の目安量をしっかり食べてくれないという場合は単純に赤ちゃんが少食な可能性もありますが、おやつ(補食)を離乳食の直前に食べ過ぎていないかなどの確認もしてみてくださいね。
完了期のスケジュール
離乳食完了期ごろの赤ちゃんでは1日3回の食事リズムを大切にして、生活リズムを整えてあげましょう。1歳を超えて離乳食をしっかり食べられている場合は、ミルクを卒業する赤ちゃんも多くなります。
おやつ(補食)は離乳食に影響が出ない時間に与え、おにぎりやいも類、果物やヨーグルトなどの食べ物を取り入れましょう。また最後の離乳食の消化や吸収が睡眠の邪魔をしないように、遅くても19時までには食べ終えるようにしてあげるのがおすすめです。
<離乳食完了期のタイムスケジュールの目安>
7時 離乳食
10時 補食(おやつ)
12時 離乳食
15時 補食(おやつ)
18時 離乳食
離乳食完了期(12〜18ヶ月)の赤ちゃんが食べられるもの
いろんな種類の食べ物を上手に食べられるようになってくる離乳食完了期。主食やおかず、副菜がそろったバランスのいい食事を意識して与えましょう。
おやつには、ママやパパが手軽に用意できる栄養のある食べ物がおすすめです。
離乳食完了期の赤ちゃんが食べられるおすすめの食べ物を紹介するので、参考にして取り入れてみてくださいね。
【主食】離乳食完了期の赤ちゃんが食べられるもの
炭水化物などの主食は、赤ちゃんの活動に必要不可欠なエネルギー源となる食べ物。離乳食完了期の主食には、軟飯やごはん、食パンやロールパン、うどんなどの麺類がおすすめです。
軟飯やごはん、食パンやロールパンは手づかみ食べしやすいようにおにぎりにしてあげたり、スティック状に切ってあげたりするのもよいでしょう。
麺類はスプーンですくいやすいように1cm幅程度の長さに切ってあげるとよいですね。
<主食向きの食べ物と1回の目安量・形状>
軟飯(80g)…おにぎり
ごはん(80g)…おにぎり
食パン(8枚切り1枚・約50g)…耳を切り落とし、1cm角かスティック状
ロールパン(35〜45g)…1cm角かスティック状
ゆでうどん(1/2玉・約100g)…1cmの長さに切る
そうめん(乾麺で60〜80g)…1cmの長さに切る
スパゲティ(40g)…1cmの長さに切る
オートミール(30〜40g)…2〜3倍の水を加えて戻す
【おかず】離乳食完了期の赤ちゃんが食べられるもの
赤ちゃんのからだを作るタンパク質を補えるおかず。肉類や魚類、大豆や大豆製品、乳製品などを離乳食でも積極的に取り入れましょう。
完了期になるとほとんどの種類の肉類や魚類を食べられるようになりますが、脂肪分の多い肉類や小骨が多い魚類、刺身や生卵などの生ものは向いていません。
自分で手づかみ食べができるように工夫してあげるのもよいでしょう。
<おかず向きの食べ物と1回の目安量・形状>
肉類(15〜20g)…加熱後小さく刻む
魚類(15〜20g)…加熱後、皮と骨を取り除き1cm角にほぐす
豆腐(50〜55g)…1cm角に切る
高野豆腐(乾物で6〜8g)…水に戻してから1cm角にする
納豆(1/2パック・約20g)…糸引き納豆もしくはひきわり納豆
卵(全卵1/2〜1/3個)…卵そぼろや卵焼きなど、しっかり加熱して与える
【副菜】離乳食完了期の赤ちゃんが食べられるもの
副菜は、からだの調子をととのえるビタミンやミネラルを補える食べ物です。野菜類やきのこ類、海藻類などの食べ物を取り入れましょう。ただし繊維が多い特徴がある野菜類やきのこ類、海藻類などの食材は、赤ちゃんが噛み切りにくいデメリットもあります。調理する際は繊維を断つように切ったり、小さく刻んであげたりする工夫を取り入れてみてください。
<副菜向きの食べ物と1回の目安量・形状>
野菜類や果物類(40〜50g)…1cm角かスティック状など
きのこ類や海藻類(少量)…細かくみじん切りにする
【おやつ】離乳食完了期の赤ちゃんが食べられるもの
離乳食の完了期では1日3回の食事に加えて、1〜2回程度のおやつ(補食)を与えます。おやつ(補食)の量は、1回の離乳食の量の1/3程度を目安にしておくのがおすすめです。
市販のお菓子を利用する場合は、1日あたり135〜140kcal程度になるように取り入れるとよいでしょう。
<おやつ向きの食べ物と1回の目安量>
おにぎり(70g)
焼き芋(50g)
牛乳(100ml)
ヨーグルト(80〜100g)
みかん(1個)
バナナ(1/2本)
離乳食完了期(12〜18ヶ月)のおすすめレシピ3選
自我が芽生え出して自分で食べたい気持ちが強くなる生後12〜18カ月ごろの離乳食完了期。手づかみ食べやスプーンを使って食べられるレシピを取り入れるとよいでしょう。
まだ上手にスプーンが使えない赤ちゃんには、食材をすくいやすいように水分量を減らしてとろみが出るように調理してあげるのもおすすめです。
「白菜とツナのクリームうどん」
【材料(1回分)】
・ゆでうどん…1/2玉(約100g)
・白菜…20g
・玉ねぎ…10g
・ツナ缶(水煮)…1/2缶(約40g)
・水…150ml
・牛乳…80ml
・コンソメ…少々
【作り方】
①ゆでうどんは1cm長さに切る。白菜と玉ねぎは1cm長さの短冊切りにする。
②鍋に白菜と玉ねぎ、ツナ缶と水を加えて弱火でやわらかくなるまで煮る。
③ゆでうどん、牛乳、コンソメを加えて弱火で5分程度煮る。
「ひじき入り豆腐ハンバーグ」
【材料(作りやすい分量)】
・鶏ひき肉…100g
・絹ごし豆腐…100g
・ひじき…少々
・にんじん…20g
・サラダ油…適量
(A)
・みそ…小さじ1/2
・砂糖…小さじ1/2
・片栗粉…大さじ1
【作り方】
①豆腐は水切りをしておく。ひじきは水で戻しておく。
②ひじきとにんじんをみじん切りにする。
③ボウルに②と鶏ひき肉、水切りした豆腐とAを加えてしっかり混ぜ合わせる。
④フライパンに油を熱し、楕円形に成形した③を両面焼く。
⑤水大さじ2(分量外)を加えて蓋をし、弱火で中に火が通るまで蒸し焼きにする。
「おやつにもおすすめ!かぼちゃ団子」
【材料(作りやすい分量)】
・かぼちゃ…100g
・きなこ…大さじ1
・砂糖…小さじ2
・片栗粉…大さじ1
【作り方】
①かぼちゃはやわらかくゆでてつぶす。
②ボウルに①ときなこ、砂糖と片栗粉を加えてしっかり混ぜ合わせる。
③鍋にお湯を沸かし、丸く成形した②を加えてゆでる。1〜2分ゆでて水を切る。
離乳食完了期(12〜18ヶ月)に関するよくある質問
ミルクだけでなく、1日3回の離乳食からほとんどの栄養を補えるようになる完了期。「噛まずに丸呑みしてしまう」「食べたものを口から出してしまう」「外食の時の離乳食はどうすればいいの?」など気になるママやパパも多いのではないでしょうか。
今回は保育園勤務の管理栄養士が、離乳食完了期の食事に関するよくある質問にお答えしていきます。
食べ物を噛まずに丸呑みしてしまいます。
食べ物を噛まずに丸呑みしてしまうと、食べるスピードも早くて心配になってしまいますよね。丸呑みしてしまう原因にはさまざまな要因が考えられますが、食事の経験を積むことで自然と治ってくるようになります。
丸呑みして吐き戻してしまったりえずいてしまう場合は、窒息予防のためにもひと口で食べられる大きさの食べ物を用意してあげるとよいでしょう。あえてかじり取って食べられる大きめの食べ物を与え、自分のひと口量を知ってもらう方法もおすすめです。
スプーンを持ちたがります。手掴みからスプーンに切り替える時期は?
赤ちゃんは生後12〜18カ月ごろになるとスプーンに興味を示すようになります。1歳を超えてスプーンを持ちたがる場合は、離乳食の時に持たせてあげるとよいでしょう。徐々にスプーンの使い方に慣れていくことで、上手に使えるようになってきます。最初のうちは手づかみ食べと並行して、スプーンで食べるメニューも組み合わせてあげるのがおすすめです。
赤ちゃんが上手にスプーン食べができないうちは、ママやパパが手を添えてサポートしてあげてみてくださいね。
食べたものを口から出してしまいます。
せっかく作った離乳食を口から出されてしまうと、悲しくなったりイライラしたりしてしまいますよね。完了期の赤ちゃんが食べ物を口から出してしまう場合は、味よりも形状に対して嫌がっている場合が多くあります。赤ちゃんの発達に合った食べやすい形状になっているか確認してみるとよいでしょう。
繊維が多い野菜類は細かくみじん切りにしてみたり、パサパサしやすい肉や魚は水溶き片栗粉でとろみをつけてあげたりすることで食べやすくなるのでぜひ試してみてください。
好き嫌いがあります。
1歳を超えると自我が芽生えるようになるため、好き嫌いが激しくなる赤ちゃんも多くなります。離乳食を見ただけで食べてくれない場合は、初めてみる食べ物に警戒している可能性もあります。普段から食べ慣れているものをベースに、食べ慣れない食材を混ぜて与えるとよいでしょう。
また苦味や酸味、青臭さの強い食べ物を嫌がるようになる時期でもあります。調理の際に少量のケチャップやマヨネーズなど、調味料を加えて苦手な味をやわらげる工夫を取り入れてみるのもよいでしょう。
じっと座って食べてくれません。
最初は座ってくれるのに、すぐに立ち上がって食べてくれなくなると困ってしまいますよね。絶対に座らせないといけないと考えてしまうと、どうしてもママやパパの精神的負担が大きくなってしまいます。
1歳や2歳のうちは動いていたい時期でもあるので、立った状態でも食べてくれているのであればよいと考えてしまうのもおすすめです。ただし寝転んだ状態で食事を与えると窒息事故の恐れもあるため避けましょう。
座って食べる機会は作り、座って食べられた時にはしっかり褒めてあげるといいですね。
下痢の時におすすめの離乳食レシピはある?
ほとんど大人と同じような食材を食べられるようになる完了期。
下痢の時は脱水状態に陥りやすくなるため、水分補給ができる消化のいい食べ物を取り入れてあげましょう。
おかゆや雑炊、汁物などのメニューがおすすめです。また食材は小さく刻んであげた方が消化に時間がかからないのでぜひ試してみてください。
胃腸が未発達な完了期では、下痢の時にかかわらず揚げ物などの脂っこい食事や刺激の強い香辛料などは避けましょう。
外食の時の離乳食はどうすればいい?
外食時の離乳食は自宅から持参する方法や、大人のメニューから取り分ける方法おすすめです。ただし外出してからすぐに離乳食食べない場合は、自宅からの持参はおすすめしません。長時間食べない可能性がある場合は菌が繁殖しやすいため、衛生面を考慮して避けましょう。
外食で大人のメニューから取り分けてあげる場合は、塩分が濃くなり過ぎてしまう可能性があります。
大人のメニューから取り分ける場合は、水で薄めて与えるなどの工夫を取り入れてみてくださいね。
離乳食完了期(12〜18ヶ月)におすすめのベビーフード にこにこ鉄分

食事から栄養をしっかり補う必要がある離乳食完了期では、「にこにこ鉄分」がおすすめです!
料理にふりかけたり、混ぜたりするだけで簡単に使える「にこにこ鉄分」は、食事だけでは不足しがちな鉄分やタンパク質、カルシウムなどの栄養素を手軽に補えます。
好き嫌いが激しかったり、離乳食をあまり食べてくれなかったりして、栄養が足りているか心配に感じているママやパパはぜひ試してみて下さいね。



おわりに
離乳食の最終ステップでもある生後12〜18カ月の離乳食完了期。
ほとんど大人と同じ食べ物を食べられるようになる時期ではありますが、かたい食べ物や味の濃い食べ物はまだ向いていません。赤ちゃんが食べやすいように、歯茎で噛み切れる程度のかたさのものを薄味にして与えてみて下さいね。
手づかみ食べだけでなくスプーン食べなどの機会も与えてあげて、赤ちゃんのペースで食事を楽しめるように見守ってあげましょう。
【ライタープロフィール】
谷岡 友梨
保育園の管理栄養士として働きながら、ママやパパからの離乳食相談や離乳食や幼児食のレシピ考案にも携わっている。
1児の娘の母として仕事と育児の両立に奮闘中。


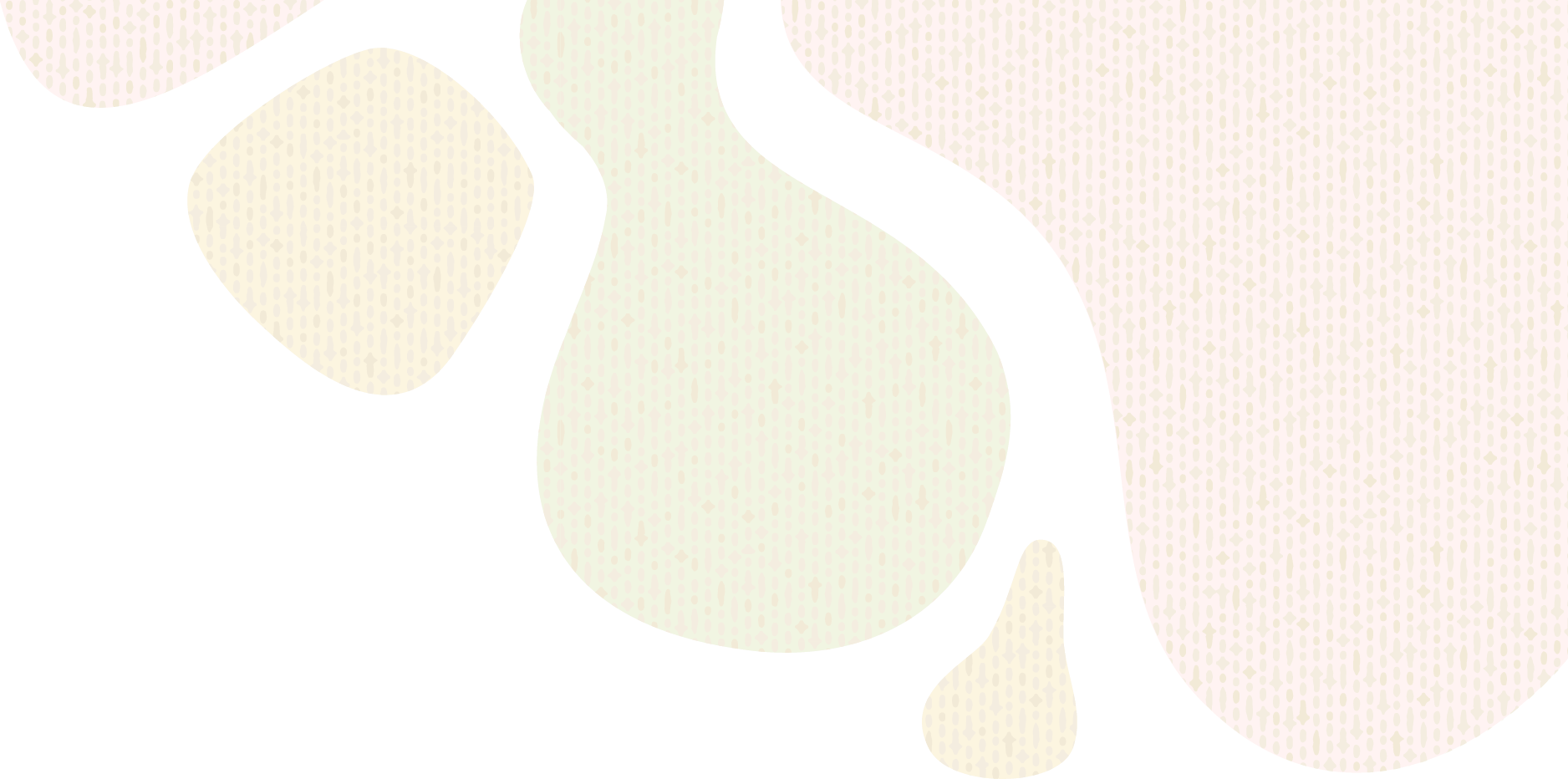










 YORISOU SHOP
YORISOU SHOP にこにこ鉄分特設サイト
にこにこ鉄分特設サイト






