【PR】

「卵はアレルギーが心配」「全卵に進む量が分からない」そんなママ・パパの声に応え、本記事では開始時期・安全手順・量の目安を月齢別に整理しました。ぜひ参考にしてみてください。
目次
卵は栄養の宝庫|鉄分やタンパク質を効率的に補う離乳食食材
卵は「完全栄養食品」と呼ばれるほど、赤ちゃんの成長に欠かせない栄養が詰まっています。
特にタンパク質・鉄分・ビタミンB群は脳や体の発達を支える重要な栄養素。母乳やミルクだけでは不足しがちな鉄分を補ううえでも、卵は心強い味方です。離乳食のメイン食材としてではなく、おかゆや野菜に少し加える栄養素の役割で取り入れると、日々の栄養バランスが整いやすくなります。
週の献立で考える「卵の位置づけ」
卵は便利な反面、毎日与えすぎると栄養バランスが偏る心配もあります。魚・豆腐・肉など他のタンパク源と組み合わせ、週に3〜4回程度を目安にすると安心。週単位で献立を考え、卵を「サポート役」と位置づけると、栄養も偏らず、家族の調理負担も減ります。
卵に含まれる「非ヘム鉄」は吸収効率に注意
卵にはタンパク質だけでなく、鉄分も含まれています。ただし、卵の鉄分は「非ヘム鉄」が中心で、体内での吸収率はそれほど高くありません。また卵白に含まれる「オボムコイド」や「リン」などが鉄の吸収を妨げることも知られています。
離乳食期は母乳の鉄が減少し、赤ちゃんが鉄不足になりやすい時期。卵だけに頼らず、赤身魚・レバー・ほうれん草など鉄分の多い食材を組み合わせることが大切です。例えば「卵としらすのおかゆ」「ほうれん草入り茶碗蒸し」などは鉄分とタンパク質を同時に摂れる良いレシピです。
卵アレルギーが起こる理由|最新ガイドラインのポイント
卵白に含まれるオボアルブミンは熱変性しても抗原性が残りやすく、乳児の腸管では未分解のまま吸収されることがアレルギー発症の主因です。
2023年改訂の日本小児アレルギー学会ガイドラインは「生後6か月から加熱卵黄を少量投与し、段階的に全卵へ移行する」ことで発症リスクを下げられると推奨しています。
【月齢別】卵の開始タイミング|初期→中期→後期→完了期
 以下では各ステップの「量・硬さ・回数」を具体的に解説します。
以下では各ステップの「量・硬さ・回数」を具体的に解説します。
下記はあくまでも目安のため、体調や便の状態を見ながら無理なく進めましょう。
初期(5–6か月):卵黄1滴からスタート
固ゆで卵の黄身を耳かき1杯分(約0.1g)取り、10倍がゆに混ぜて午前中に与えます。
問題がなければ小さじ1/4へ増量。
中期(7–8か月):卵黄→全卵1/4量へ
卵黄を小さじ1までクリアしたら、固ゆで全卵の1/8量(約5g)を細かく潰してとろみ野菜と和えます。
3日かけて1/4量(10g)へ。
後期(9–11か月):全卵1/2個
手づかみ食べが始まる頃。オムレツや卵焼きで全卵1/2個を週3回までOK。
まだ半熟は避け、中心までしっかり火を通します。
完了期(12か月〜):全卵1個OK&週3回まで
噛む力が安定したら全卵1個(50g)を目安に。
半熟のスクランブルや茶碗蒸しも段階的に挑戦可能です。ただし連日多量摂取は避け、魚や豆も組み合わせてバランスを取りましょう。
初めての卵で注意すべきサインと対処法
食後4時間以内にじんましん・嘔吐・咳が出たら医療機関へ。
顔が赤くなる軽微な反応でも、初回は写真を撮って小児科で相談すると安心です。
よくある卵のQ&A
Q. 卵は固ゆで必須?
A. 初期〜後期までは固ゆで推奨。完了期から半熟に移行可能。
Q. 茹で卵は冷凍できる?
A. 卵黄のみペースト状にして冷凍可。1週間以内に使い切る。
Q. 卵アレルギーがある兄弟がいる場合は?
A. 血液検査より食物経口負荷試験が推奨。必ず専門医に相談を。
卵だけじゃない!鉄分も意識した離乳食へ

卵デビューが進む頃、実は鉄分が急激に不足しやすい時期でもあります。
レバーや赤身魚を毎日食べさせるのは大変...そんなときは、無味無臭の粉末サプリ〈にこにこ鉄分〉がおすすめです。
1包で4.5mgの鉄分を手軽にプラスでき、赤ちゃんの成長とママの産後ケアを一緒にサポートします。

まとめ|卵は少量から段階的に、必ず加熱しよう
卵は卵黄1滴からゆっくり増やし、全卵デビュー後も週3回までが安心ライン。
加熱・時間帯・アレルギーサインを守りながら、同時に鉄分不足にも目を配れば、離乳食はグッとラクになります。
今日のメニューに〈にこにこ鉄分〉を加えて、卵も鉄も賢くクリアしましょう。
よくある質問
Q.子どもが鉄分不足になると、どんな症状がありますか?
A.貧血(顔色が悪い、疲れやすい)、集中力低下、食欲不振、イライラしやすいなどの症状が出ることがあります。
Q.子どもに必要な鉄分の摂取量はどれくらいですか?
A.1~2歳で約4.5mg、3~5歳で約5.5mgが目安です。食事からの摂取が基本です。
Q.鉄分を多く含む食材には何がありますか?
A.レバー、赤身肉、しらす、かつお、ほうれん草、小松菜、大豆製品などが挙げられます。
Q.子どもが鉄分の多い食材を嫌がる場合、どうしたらいいですか?
A.ハンバーグやお好み焼きに混ぜたり、スープにするなど調理を工夫するのがおすすめです。
Q.鉄分のサプリメントは子どもに飲ませても大丈夫ですか?
A.1日の推奨量の範囲内であれば問題ありません。にこにこ鉄分は1日1包、親子で利用することが可能です。


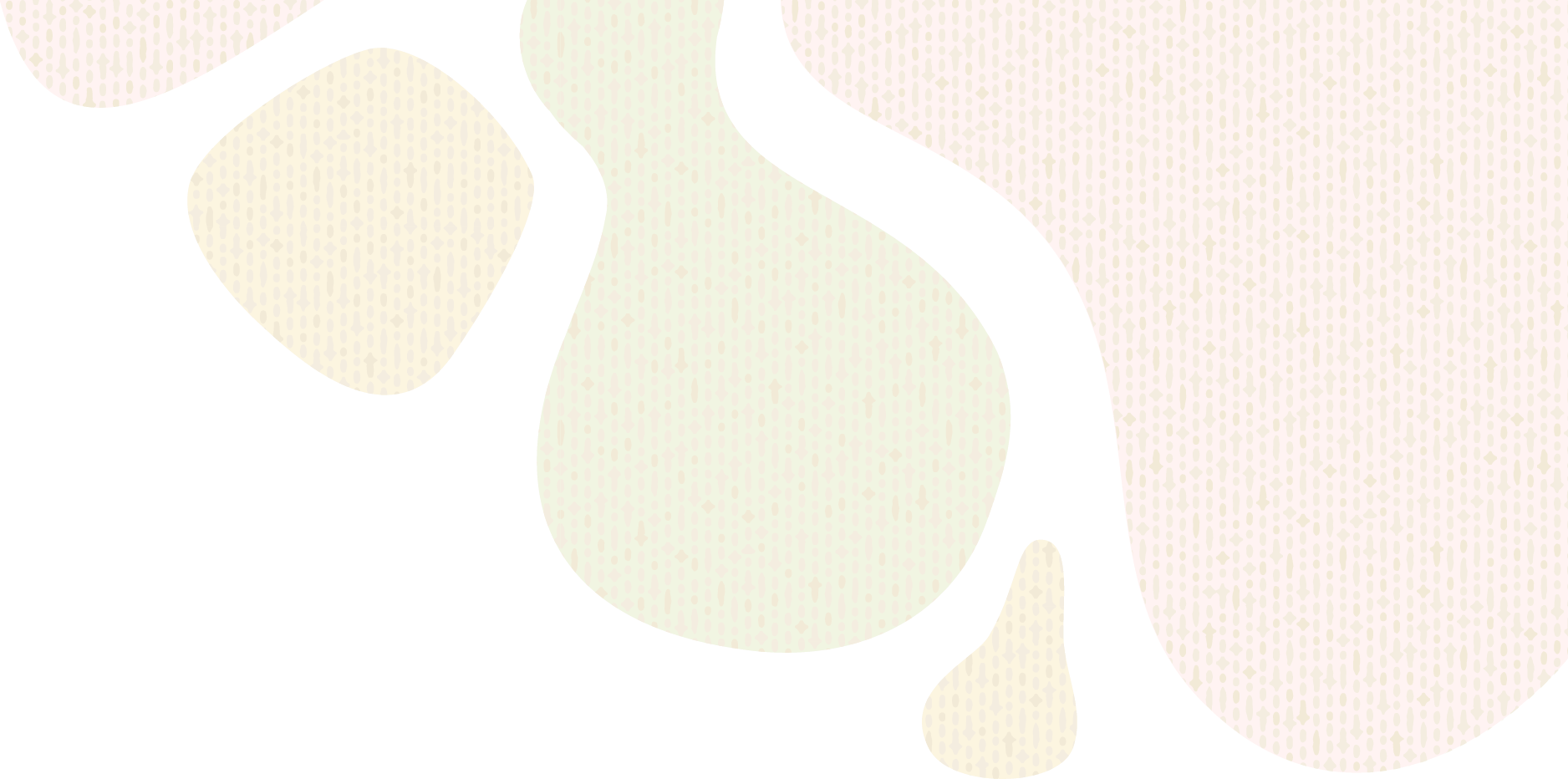











 YORISOU SHOP
YORISOU SHOP にこにこ鉄分特設サイト
にこにこ鉄分特設サイト





