【PR】
「発達障害と偏食は関係があるの?」と不安に思う保護者の方は少なくありません。
発達障害のある子どもは、感覚の敏感さやこだわりの強さから食べられるものが限られることがあります。
ここでは、偏食の特徴や背景、栄養への影響、家庭でできる工夫や相談先まで整理しました。
発達障害と偏食
自我が芽生える1歳ごろから5歳ごろまでに多く見られる偏食。
子供の偏食は自然と改善していくことがほとんどですが、かたよった食事が続くと栄養不足になったり健康に影響したりする可能性があるので普段の食事で偏食対策を取り入れてみるのもよいでしょう。
偏食は自閉スペクトラム症やアスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害などの発達障害がある場合にも多くみられます。
発達障害がある場合は、嫌がる食べ物を無理に食べさせることで強いストレスがかかってしまうので注意が必要です。
子供の特性に合わせた対策を取り入れてあげるのがよいでしょう。
また知能機能が一般よりも低い状態の境界知能は、発達障害とは概念が違っています。
境界知能の場合は発達障害のような特性が見られませんが、境界知能で偏食がある場合は発達障害の偏食対策を参考にしてみるのもよいでしょう。
発達障害と偏食の関係
発達障害の子どもに偏食が多く見られるのは事実ですが、すべての子に当てはまるわけではありません。
特にASD(自閉スペクトラム症)では感覚過敏やこだわりが強く、ADHDでは食事中の集中力が続きにくい傾向があります。
発達障害を持つ子供の偏食の原因
発達障害を持つ子供は、感覚過敏によって食事をうまく食べられないことがあります。
また偏食はこだわりが強かったり、口腔機能が未発達であることなども原因のひとつとして考えられます。
まずは子供が何に嫌がっているのかを知ってから、偏食対策を取り入れるとよいでしょう。
偏食の原因①:感覚過敏
感覚過敏は音や光、触覚や味覚、匂いなどの刺激に対して過剰な反応や過敏な反応が現れる症状で、神経発達の問題や神経系の異常、発達障害などがある場合に引き起こされる症状です。感覚過敏の症状は子供によって違っているので、何に対して過敏に反応してしまっているのか理解しておくとよいでしょう。
偏食の原因①-1:視覚過敏
視覚過敏は、光や色、モノの見た目に対して過敏に反応する特性のことをいいます。食べ物の見た目や食器の色などが好みではないと、特定の食べ物を避けたり食事を摂ってくれなかったりすることがあるので調理や盛り付け、使う食器類などに工夫が必要です。
・いちごの粒々が気持ち悪い
・白色の食べ物は食べられるが、緑や赤の食べ物は食べられない
・特定の色の食器やスプーンであれば食べられる など
偏食の原因①-2:味覚過敏
発達障害を持つ子供で味覚過敏によって偏食がある場合は、特定の食べ物の味に対して過敏な反応が現れます。食べ物の苦味や酸味、塩味や甘味などに対して過剰な反応や不快感を示すため、嫌がる場合は特定の苦手な味をやわらげてあげるとよいでしょう。
また食べ慣れていない新しい料理を避けやすいので、いつも同じメニューになってしまう特徴もあります。
・辛い食べ物を食べると痛みを感じる
・酸味や苦味がある食べ物は気分が悪くなる
・食べ物の味を濃く感じやすい
・新しい料理や食べ物を受け付けない など
偏食の原因①-3:触覚過敏
発達障害を持つ子供で触覚過敏がある場合は、特定の食べ物の食感や温度に対して過敏な反応を示すために偏食が起こる可能性があります。また特定の素材や苦手な形状の食器や食具を避けることもあるため、触覚過敏がある場合は使う食器や食具が子供に合っているかどうかも確認してみるとよいでしょう。
・コロッケの衣がチクチクして苦手
・ネバネバやドロドロした口当たりのものを避ける
・きのこのツルツル感や弾力がゴムのように感じる
・じゃがいものホクホク感が苦手 など
偏食の原因①-4:嗅覚過敏
発達障害を持つ子供で嗅覚過敏があると、特定の匂いに対して過敏な反応を示すために偏食が起こることがあります。苦手な匂いに対して不快感を感じやすいため、その匂いがする食べ物を避けたり食事を摂りたがらなかったりする可能性もあります。
・料理中の匂いを嫌がる
・臭みのある発酵食品
・酸味や苦味が強い食べ物を避ける など
偏食の原因①-5:聴覚過敏
発達障害を持つ子供で聴覚過敏がある場合は、外部からの音に対して不快感や痛みを感じるなどの反応を示すことがあります。音によるストレスによって食事中の集中力が切れたり、ストレスがかかることで食欲が低下してしまったりする可能性があります。
・時計の秒針の音が気になって食事に集中できない
・食器が触れ合う音を嫌がる など
偏食の原因①-6:固有受容覚過敏
発達障害を持つ子供で固有受容覚過敏がある場合は、身体の動きや力の入れ具合に対して敏感に反応してしまいます。食事中に使われる食器や食具、椅子などの身体に触れるものに対して過敏に反応して、必要以上に力を入れてしまったり、逆に力が弱すぎてしまったりすることがあります。
上手に食べられないことから偏食につながる可能性もあるので、食べやすいように対策してあげるとよいでしょう。
・食事をする際の力加減が難しい
・モノを落としたりこぼしたりしやすい など
偏食の原因②:こだわりが強い
発達障害を持つ子供の偏食は、こだわりの強さが原因である場合もあります。こだわりが強いと特定の食べ物しか食べてくれなかったり、決まったルーティンでの食事を好む傾向があったりします。
・食事の料理や時間、場所について自分のルールがある
・食べ慣れない料理は食べない
・特定の食器でないと食事を嫌がる
・汁物を食べてからでないとごはんが食べられない など
発達障害を持つ子供の偏食の対策
発達障害による感覚過敏やこだわりの強さがある場合は、無理に食べさせようとすると大きなストレスがかかってしまいます。
発達障害を持つ子供の偏食対策は、子供の特性に合わせて行うことが重要です。
それぞれの特性に合わせた偏食対策を紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
偏食の対策方法①:感覚過敏
視覚や味覚、触覚や嗅覚、聴覚や身体の動きや位置を感じる固有受容覚に対して、過敏に反応してしまう感覚過敏。発達障害を持つ子供で感覚過敏がある場合は、食事を嫌がる原因として考えられるものを避ける偏食対策がおすすめです。
偏食の対策方法①-1:視覚過敏
発達障害を持つ子供で視覚過敏がある場合の偏食対策には、食べ物の見た目を工夫したり食器やスプーンなどの色や素材を好みのものに変えてあげたりする方法がおすすめです。・いちごはミキサーにかけてつぶし、ジュースにする
・食べられない色は刻んで食べられる色の食材に混ぜる
・無地の食器やスプーンを使用する など
偏食の対策方法①-2:味覚過敏
発達障害を持つ子供で食べ物の味に対して過剰に反応してしまっている味覚過敏がある場合は、好みの味付けに変えてみたり刺激の少ない食べ物を取り入れてみたりする偏食対策がおすすめです。・好みの調味料を使う
・初めて与える料理は材料や作り方、味などを説明する
・金属製のスプーンを木製スプーンに変える など
偏食の対策方法①-3:触覚過敏
発達障害を持つ子供で、特定の食べ物の食感や温度に対して過敏な反応を示す触覚過敏がある場合は、食べられるように調理や盛り付けの工夫を取り入れる偏食対策がおすすめです。また食器やスプーンが子供に合っているかどうかも確認してみるとよいでしょう。・食べられる食感の料理にする
・ハンバーガーやエビフライなど複数の食感が混ざっているものは、別々に分けて盛り付ける
・カレーのごはんとルウは別盛りにする
・料理の温度は子供が食べやすい温度に冷ましたり温めたりする など
偏食の対策方法①-4:嗅覚過敏
特定の匂いに対して過敏な反応を示す嗅覚過敏。発達障害を持つ子供で嗅覚過敏がある場合は、苦手な匂いによってストレスがかからないように工夫する偏食対策がよいでしょう。
・料理中の匂いが嫌な場合は別の部屋で待つ
・臭みのある発酵食品や酸味の強い食べ物を避ける など
偏食の対策方法①-5:聴覚過敏
外部からの音に対して、不快感や痛みを感じるなどの反応を示す聴覚過敏。発達障害を持つ子供で聴覚過敏がある場合は、ストレスがかからない食事環境をととのえる必要があります。
・テレビや電子機器の音が聞こえないようにする
・陶器ではなくプラスチックの食器やスプーンを使う など
偏食の対策方法①-6:固有受容覚過敏
食器や食事中の椅子など、身体に触れるものに対して過敏に反応する固有受容覚過敏。発達障害を持つ子供で固有受容覚過敏による偏食が強い場合は、使用する食器やスプーンを使いやすいものにしたり食事環境の工夫を取り入れたりする対策がよいでしょう。
偏食の対策方法②:こだわりが強い
発達障害を持つ子供では、特定の味や食感の食べ物しか食べない、決められたルーティンでしか食事を摂りたくないなどのこだわりが強いことも多く見られます。あらかじめどんな料理を用意したのかを説明したり、食事の準備や手順をルーティン化してあげたりする偏食対策がおすすめです。
調理方法を工夫してみる
発達障害を持つ子供で感覚過敏やこだわりが強い特性が見られる場合には、子供の特性に合わせて食べやすいように調理方法を工夫してみましょう。やわらかい食べ物が苦手な場合は、揚げ物にしてかたさを残す。特定の色の食べ物しか食べない場合は、苦手な色がわからないようにみじん切りにして混ぜてあげるなどの調理の工夫もおすすめです。
偏食による栄養不足が与える影響と対策
偏食の悪影響
鉄分不足:集中力低下や発達の遅れにつながることがあるビタミン・ミネラル不足:免疫低下や体調不良のリスク
たんぱく質不足:成長に必要な栄養が不足する可能性
家庭でできる偏食対策
・食材の切り方や加熱方法を変えてみる・少量を繰り返し出して「慣れ」を促す
・盛り付けや器を工夫して興味を引く
・無理に食べさせず、子どものペースを尊重する
栄養補助食品やサプリの活用
どうしても食事だけで必要な栄養を補えない場合は、鉄分やビタミンを含むサプリメントを活用するのも一つの方法です。偏食対策におすすめの にこにこ鉄分
発達障害のある子どもは、鉄分やビタミンを含む食材をなかなか受け入れられないことがあります。そんなとき、日常の食事にさっと加えられる栄養補助食品を取り入れるのも一つの方法です。
にこにこ鉄分は、無味無臭の粉末タイプで、おかゆやスープ、ヨーグルトなどに混ぜるだけで鉄分を補うことができます。
1包に鉄分4.5mgを配合し、吸収を助けるビタミンCや葉酸も一緒に摂れるのが特長です。さらに砂糖・着色料・保存料は不使用、国内のGMP認定工場で製造しているため、安心して続けられます。
「鉄分をとらせたいけれど、子どもが鉄の味に敏感で嫌がる…」というご家庭でも、にこにこ鉄分なら食事の味を変えずに自然に取り入れられるため、偏食対応のサポートとして役立ちます。
子供の偏食対策におすすめのレシピ2選
栄養バランスを考えて用意した料理でも、子供が食べてくれないと悩んでしまいますよね。
今回は子供の偏食対策におすすめのレシピを紹介します。
レシピ①「かぼちゃシチュー」
【材料(3人分)】
・ツナ缶(水煮)…1缶(70g)
・かぼちゃ…50g
・玉ねぎ…1/2個
・サラダ油…適量
・小麦粉…小さじ2
・水…150cc
・コンソメ…小さじ1
・無調整豆乳…200cc
・塩…少々
【作り方】
①かぼちゃは包丁で皮を削ぎ落とし、1.5cm角に切る。玉ねぎは1cm角にする。
②鍋にサラダ油を熱して①とツナを加え、玉ねぎがアメ色になるまで炒める。
③一旦火を止め、小麦粉を振り入れて全体に絡むように混ぜ合わせる。
④再度弱火にして水、コンソメを加えて食材に火が通るまで加熱する。
⑤無調整豆乳と塩を加えて味をととのえる。
レシピ②「ブロッコリーのチーズ焼き」
【材料(2人分)】
・ブロッコリー…40g
・じゃがいも…中1/2個
・片栗粉…大さじ1/2
・ピザ用チーズ…大さじ1
・サラダ油…適量
【作り方】
①ブロッコリーは小房に切る。じゃがいもは千切りにする。
②ボウルに①と片栗粉、ピザ用チーズを加えてしっかり混ぜ合わせる。
③フライパンに油を熱し、②を流し入れて片面に焼き色がついたらひっくり返す。
④水大さじ2(分量外)を加えて蓋をし、弱火〜中火で蒸し焼きにする。
おわりに
発達障害による感覚過敏やこだわりの強さがある子供に、苦手な食べ物を無理やり食べさせると精神的や身体的に大きな負担がかかってしまいます。
子供の特性に合わせて調理の工夫を取り入れて、楽しい雰囲気で食事をすることを意識しておくといいですね。
この記事を参考に、発達障害を持つ子供への偏食対策をぜひ取り入れてみてくださいね。
ライタープロフィール
谷岡 友梨
保育園の管理栄養士として働きながら、ママやパパからの離乳食相談や離乳食や幼児食のレシピ考案にも携わっている。
1児の娘の母として仕事と育児の両立に奮闘中。


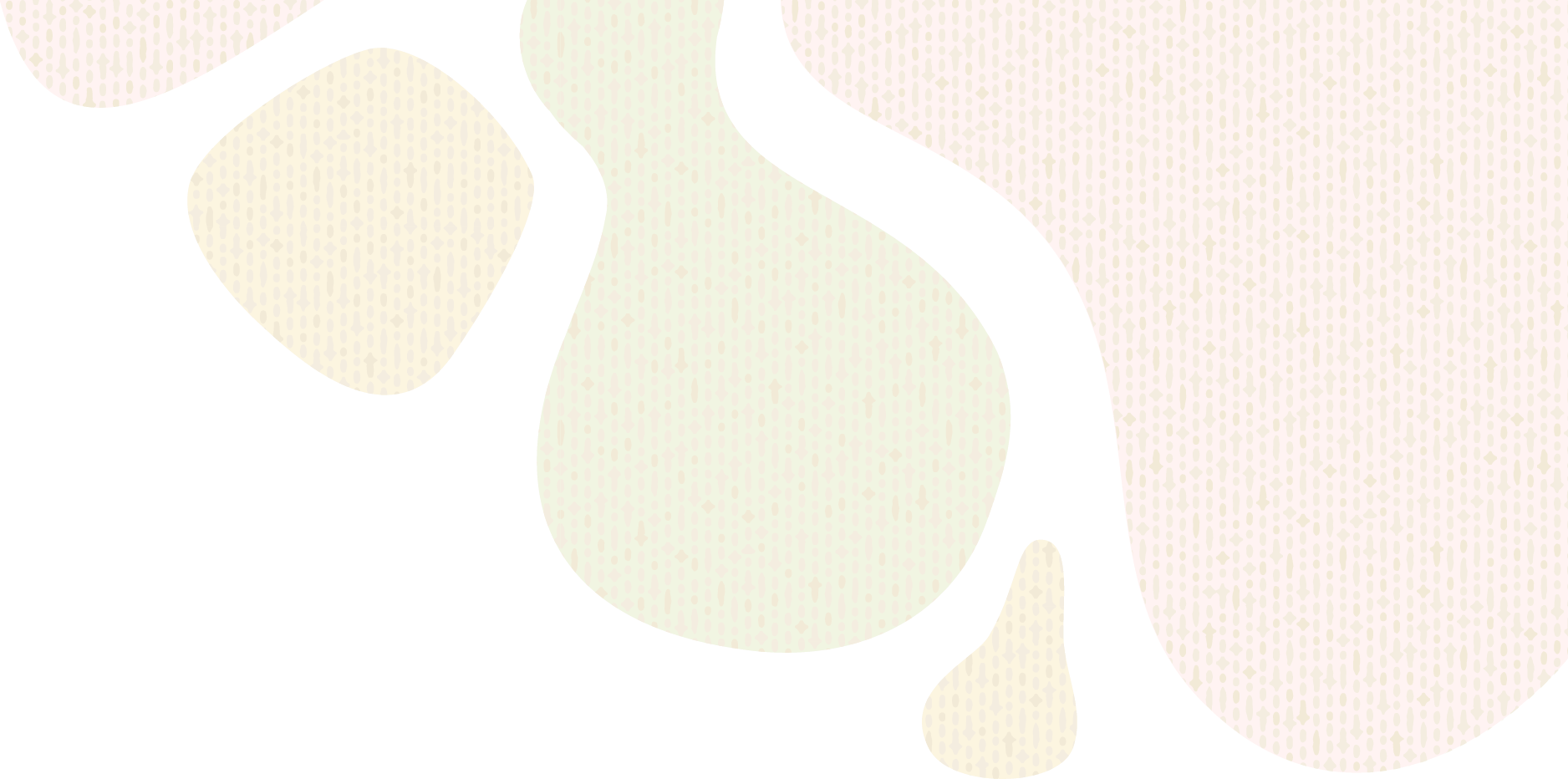











 にこにこ鉄分特設サイト
にこにこ鉄分特設サイト





