【PR】
1歳を過ぎた赤ちゃんは離乳食を卒業し、いよいよ「幼児食」へとステップアップする時期です。
しかし、幼児食は離乳食とどう違うのか、どんな食材や量を与えればよいのか、不安に感じる保護者の方も多いでしょう。
この記事では、幼児食の基礎知識から、年齢別の食事量の目安、栄養バランスの整え方、簡単な献立例、さらに不足しがちな鉄分の補い方までを丁寧に解説します。
幼児食とは?離乳食との違い

幼児食は、離乳食を卒業した1歳〜6歳ごろまでの子どもが対象の食事を指します。
家族と同じ食事を「一緒に」楽しみながら、栄養や味、食べる楽しさを覚えていく大切な時期です。
離乳食が“飲み込みやすさ・やわらかさ”を重視していたのに対し、幼児食では“噛む力・味覚・栄養バランス”の育成が目的となります。
幼児食はいつからいつまで?
一般的に幼児食は、1歳〜1歳半ごろからスタートし、6歳ごろまでが目安です。
ただし、子どもの発達スピードには個人差があるため、歯の生え方・咀嚼の様子・食べる意欲などを見ながら進めていくのが大切です。
幼児食の1回の量と食事回数の目安
幼児食の目安量は、1日3食+必要に応じて1〜2回のおやつ。1回の量の目安は以下の通りです。
おやつは補食と考え、エネルギーや栄養を補えるものを選びましょう。
・主食(ごはんなど):80〜100g
・主菜(肉・魚・卵など):40〜50g
・副菜(野菜・きのこなど):40〜50g
・汁物・果物:適量
年齢別の食事量と栄養素の目安
1歳半〜3歳:ごはん80〜100g、野菜40g、肉・魚15〜20g
4〜5歳:ごはん120〜140g、野菜60〜70g、肉・魚30g
栄養素では、鉄分・カルシウム・ビタミンD・DHAなど不足しがちなものを意識すると安心です。
偏食や遊び食べの対応
好き嫌いや遊び食べは成長過程でよく見られるものです。
無理に食べさせるよりも、少量を繰り返し出すことで徐々に慣れていきます。調理法を変えたり、盛り付けを工夫するのも有効です。
食習慣を自立につなげる工夫
幼児食は栄養だけでなく「自分で食べる力」を育む時期です。
手づかみ食べやスプーンの練習を通じて、食事への意欲や自立心を養えます。
幼児食で意識したい栄養バランス
幼児期は、成長が著しく、栄養不足や偏りが心身の発達に大きく影響することもあります。ポイントは以下の3つです。
1:主食・主菜・副菜をバランスよく
2:塩分・糖分・脂質は控えめに
3:鉄分・カルシウム・ビタミンDなどの不足に注意
特に鉄分は意識して摂らせたい栄養素。
体内の貯蔵鉄が少なくなる時期のため、赤身肉や大豆製品など鉄分を多く含む食材を積極的に取り入れましょう。
幼児食におすすめの簡単献立例
朝食:やわらかごはん+納豆+ゆで卵+バナナ+味噌汁
昼食:ツナと野菜のうどん+スティック野菜+ヨーグルト
夕食:鶏ひき肉入りハンバーグ+ほうれん草のごま和え+ごはん+豆腐の味噌汁
おやつ:おにぎり/蒸しパン/にこにこ鉄分入りヨーグルト など
おやつ(補食)の役割
おやつは「甘い楽しみ」だけではなく、1日3食で不足しがちな栄養を補う「第4の食事」として大切です。
エネルギー源になるおにぎりや、カルシウムを含むヨーグルトなどを選ぶと、栄養バランスが整いやすくなります。
鉄分不足を感じたら「にこにこ鉄分」を活用

1〜2歳の子どもは鉄分不足になりやすく、貧血や発育への影響が心配されます。
「にこにこ鉄分」は、成長期の子ども向けに開発された鉄分補助食品で、無味無臭の粉末タイプ。
ごはんやスープ、ヨーグルトに混ぜるだけで、自然に鉄分をプラスできます。
栄養の偏りが気になるとき、毎日のメニューに簡単に取り入れられる安心のサポートアイテムとしておすすめです。
よくある質問
Q:子どもが鉄分不足になると、どんな症状がありますか?
貧血(顔色が悪い、疲れやすい)、集中力低下、食欲不振、イライラしやすいなどの症状が出ることがあります。
Q:子どもに必要な鉄分の摂取量はどれくらいですか?
1~2歳で約4.5mg、3~5歳で約5.5mgが目安です。食事からの摂取が基本です。
Q:鉄分を多く含む食材には何がありますか?
レバー、赤身肉、しらす、かつお、ほうれん草、小松菜、大豆製品などが挙げられます。
Q:子どもが鉄分の多い食材を嫌がる場合、どうしたらいいですか?
ハンバーグやお好み焼きに混ぜたり、スープにするなど調理を工夫するのがおすすめです。
Q:鉄分のサプリメントは子どもに飲ませても大丈夫ですか?
1日の推奨量の範囲内であれば問題ありません。にこにこ鉄分は1日1包、親子で利用することが可能です。
まとめ|幼児食は「家族と食べる楽しさ」を育む時期
幼児食は、単なる食事ではなく「食べる力・栄養・心の成長」を支える大切な時期。
量や栄養バランスに気を配りつつ、親子で食卓を囲む時間を大切にして、楽しく健康的な食生活を築いていきましょう。


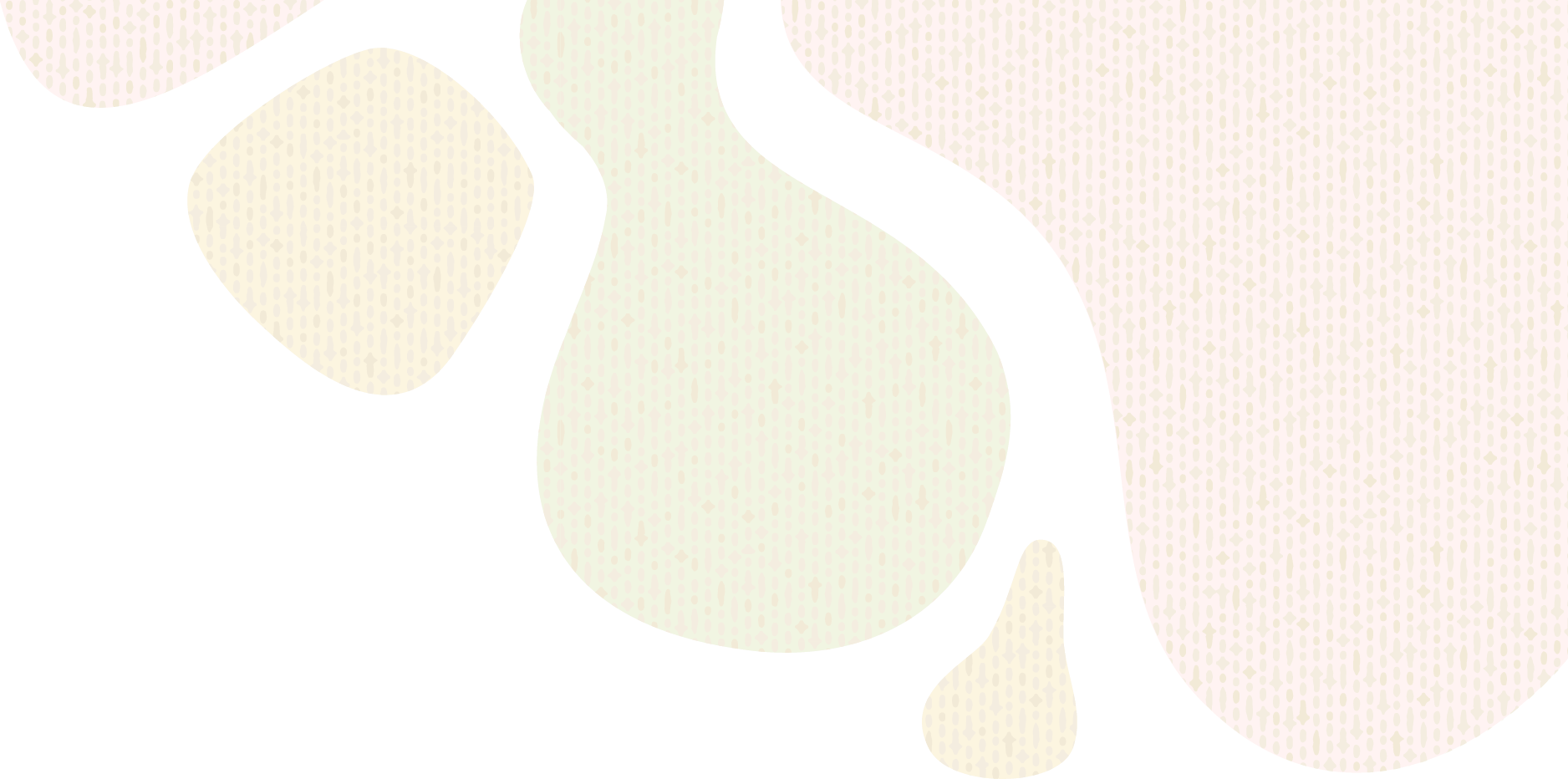










 YORISOU SHOP
YORISOU SHOP にこにこ鉄分特設サイト
にこにこ鉄分特設サイト





