【PR】
赤ちゃんの夜泣きに悩んでいませんか?
毎晩泣き続ける我が子を前に、どうして泣き止まないのか原因がわからず不安になるママ・パパも多いはずです。
この記事では、赤ちゃんが夜泣きをする主な原因をわかりやすく解説し、今日からできる対策方法も紹介します。

夜泣きとは

夜泣きとは、赤ちゃんが夜間に突然目を覚まし、泣き出してしまう現象のことを指します。
特に生後6ヶ月頃から1歳半くらいまでの間に多く見られ、日中は元気でも夜だけ泣くのが特徴です。
夜泣きは赤ちゃんの発達過程のひとつであり、病気ではないことがほとんどですが、原因がはっきりしないことが多いため、ママ・パパにとっては大きなストレス要因になります。
まずは夜泣きの基本的な特徴を理解し、落ち着いて対応することが大切です。
【参考文献】
熊本大学教育学部看護課程『乳児夜泣きの要因分析』成田栄子著
夜泣きの原因
「赤子は泣き泣き育つ」との言葉がありますが、多くのパパ・ママが赤ちゃんの夜泣きにまいっていることでしょう。
「どうして、毎日夜中に泣くんだろう」と、理由がわからず途方に暮れてしまいますよね。
赤ちゃんがなぜ夜泣きするのかよくわかっていませんが、主に次の3つが原因と考えられています。
-
①赤ちゃんが不快感を訴えているから
-
②睡眠が未熟だから
-
③日中の刺激が処理できていないから
夜泣きの原因1|不快感を訴えている
赤ちゃんが夜泣きするのは、何かしら嫌な感覚を感じて周りの人に訴えているのかもしれません。
たとえば、お腹が空いた、喉が渇いた、オムツが濡れて気持ち悪いなど、不快感を訴えている場合があります。
赤ちゃんは不快感をおぼえても、自分では何もできません。そのため大声で泣いて、誰かに助けを求めるのです。
夜中も同様で、何かしらの不快感を訴えるために夜泣きしているケースも少なくありません。
夜泣きの原因2|睡眠が未熟

赤ちゃんは、睡眠のリズムがまだ発達段階にあります。睡眠リズムがまだ整っていないため、夜泣きにつながっている可能性があるのです。
人の睡眠は、浅い眠りの「ノンレム睡眠」と深い眠りの「レム睡眠」があり、入眠中に二つの睡眠を繰り返します。
赤ちゃんの場合レム睡眠の比率が大人より長く、睡眠サイクルも短い周期で繰り返されます。
浅い睡眠である「ノンレム睡眠」の時間が長いため、少しの刺激ですぐに起きてしまうのです。
眠いのに目が覚めてしまった場合、眠くて泣いている可能性も考えられます。
夜泣きの原因3|日中の刺激が処理できていない
人は日中に経験した出来事を、入眠中に脳内で整理して記憶として定着させます。
しかし赤ちゃんは、初めて体験することばかりです。加えて脳が発達の途中なので、情報の整理が追いつきません。
夜眠ろうとしても、脳が活発になって興奮しているため、夜泣きしてしまうのです。
とはいえ、この状態は赤ちゃんの脳が成長している証拠です。この種の夜泣きは、成長とともに徐々に収まってくるでしょう。
年齢別|夜泣きの原因と対策
赤ちゃんの夜泣きは月齢や年齢によって原因が異なります。
生後3〜6ヶ月頃は昼夜の区別がついておらず、睡眠リズムが不安定なため夜泣きしやすい時期です。
1歳前後では、日中の刺激や分離不安が影響しやすくなります。
2歳を過ぎると、記憶力や感情が発達することで、夢や不安による夜泣きも増えます。
年齢ごとの特徴を理解した上で、赤ちゃんに合った対策を取ることが大切です。
たとえば、生活リズムの見直しや安心できる就寝環境の工夫、鉄分など栄養面のサポートも効果的です。
以下は年齢別の夜泣きの主な原因と対策です。参考にぜひ試してみてください。
| 年齢 | 主な原因 | 対策 |
|---|---|---|
|
生後3〜6ヶ月 |
昼夜の区別が未発達で睡眠リズムが安定していない |
日中の明るさ・夜間の暗さを意識した生活リズムの確立 |
|
生後7〜11ヶ月 |
分離不安や寝返り・はいはいなどの発達による刺激 |
寝かしつけのルーティンを作り、安心できる環境を整える |
|
1歳〜1歳半 |
記憶や感情の発達による夢・不安や環境の変化 |
穏やかな語りかけや絵本の読み聞かせなど、安心感のある就寝習慣を |
|
1歳半〜2歳以降 |
自我の芽生え、イヤイヤ期によるストレスや疲れ |
日中の活動バランスを見直し、栄養や睡眠の質を意識 |
先輩ママさんおすすめの夜泣き対策
不快に感じていることを取り除く
赤ちゃんのオムツがおしっこやうんちで濡れていると、不快感を訴えて夜泣きが始まります。
そのほかに部屋が暑かったり寒かったりする場合も、夜泣きして不快感を訴えるでしょう。
そのため、赤ちゃんが不快感を訴えているようなら、不快に感じていることを取り除いてあげてください。
排泄しているようならオムツをかえてあげ、汗をかいている場合は着替えをしましょう。それだけで泣き止むこともあります。
また赤ちゃんが不快を感じている際に「ソワソワ」する「きょろきょろ」するなど、なにかしらサインを送るケースもあります。
サインが出たらすぐに対応すれば、夜泣きせずにぐっすり眠ってくれる場合もありますよ。
赤ちゃんを抱っこする・授乳する
赤ちゃんは水分保持能力が低くそのうえ汗かきのため、すぐにのどが渇きます。
そのため、寝る前に授乳するのがいいでしょう。入眠前に水分を補給すれば、のどの渇きで夜泣きする機会も少なくなります。
また授乳すると、親と触れ合えている安心感を感じて寝てくれます。
夜泣きの原因がのどの渇きや空腹ではなかったとしても、スキンシップは赤ちゃんに安心感を与えてくれるでしょう。
安心する音を聞かせる
赤ちゃんがお腹の中にいたときに聞いた音を聞くと、夜泣きが止まる場合があります。
たとえば、掃除機の音やテレビの砂嵐音(ザーザー音)、ドライヤーの音などが効果あるようです。
他にも特定の曲で落ちつく赤ちゃんも、少なくありません。
「ムーニーちゃんのおまじない」や「タケモトピアノのCM」「反町隆史さんのPOISON」などが、赤ちゃんが泣き止むと話題です。
また、赤ちゃんが泣き止む音を集めたアプリやYouTubeチャンネルもあります。一度試してはいかがでしょうか。
鉄分が不足も夜泣きの原因?

夜泣きの原因として意外と見落とされがちなのが「鉄分不足」です。
鉄は赤ちゃんの脳や神経の発達に欠かせない栄養素で、特に生後6ヶ月頃から母乳やミルクだけでは不足しがちになります。
鉄分が不足すると、イライラしやすくなったり、眠りが浅くなることが知られています。
夜泣きがなかなか改善しない場合、環境や習慣だけでなく、栄養面の見直しも一度検討してみるのがおすすめです。
鉄分不足と赤ちゃんのイライラ・睡眠の関係
鉄分は酸素を運ぶヘモグロビンの材料で、脳の働きにも深く関わっています。
鉄分が不足すると、赤ちゃんはイライラしやすくなったり、ぐずる時間が増えることがあります。
また、睡眠が浅くなる傾向も報告されており、夜泣きが悪化する原因になることも。
普段の食事から鉄分を意識的に補うことは、赤ちゃんの穏やかな気持ちや安定した睡眠をサポートする大切なポイントです。
鉄分補給が役立つケースを紹介
鉄分補給が役立つのは、特に離乳食が始まった赤ちゃんや、偏食がちな子ども、母乳中心で育っている場合です。
これらのケースでは、食事だけで十分な鉄分を摂るのが難しいことがあります。
そんなとき、無理なく鉄分をプラスできるサプリや食品が強い味方になります。
鉄分補給によって、夜泣きが改善したと感じる保護者の声も多く、試す価値のある対策です。
にこにこ鉄分の安心ポイント
子どもの鉄分、足りてますか?子供の脳は6歳までに90%が完成するといわれており、その中でも鉄分はとても重要な役割を担っています。
しかし、鉄分の豊富な食材は子供の苦手なものばかり、子どもは口に入れてくれません。
「にこにこ鉄分」はさっと溶けるので、子どもに気付かれずに鉄分豊富な料理が作れます。
にこにこ鉄分でしっかり栄養を与えて、愛するこどもの成長をサポートしましょう。

赤ちゃんの夜泣きはいつまで続く?
赤ちゃんの夜泣きは一般的に、生後8〜10か月ごろにピークを迎え、大体1歳半〜2歳ごろに終わります。
2歳を過ぎても治らない場合は、なんらかのトラブルを抱えている可能性もあります。
まずはかかりつけの小児科医に相談してみましょう。
逆効果!やってはいけない夜泣き対策
赤ちゃんが夜泣きするたびに授乳するのは、良くありません。夜泣きのたびに授乳すると、結構な量のミルクを飲んでしまいます。
朝の食欲にも影響するため、できるだけ夜中は麦茶や白湯にして、授乳はどうしても泣き止まないときだけにしましょう。
また、赤ちゃんが泣き止まない場合、イライラしてしまいその場を離れることもあるでしょう。落ちつくまでの間、少し離れるのは問題ありません。
しかし長時間放置するのはよくありません。 赤ちゃんとの信頼関係は、スキンシップを通して作られます。
そのため、長時間無視すると赤ちゃんは「愛されていない」と不安になってしまうでしょう。
たとえすぐに対応できない場合でも「少しまってね」と、声をかけてあげましょう。
まとめ

赤ちゃんの夜泣きの原因は、はっきりとはわかっていません。
しかし、オムツをかえる。抱っこして授乳する。好きな音楽を流すなど、効果のある方法はいくつかあります。
また、日ごろから生活リズムを整えたり、日中の活動を活発にすることも必要でしょう。
とはいえ、いくら頑張っても、夜泣きがピタッと止まることはありません。
そのため、夜泣きへの向き合い方やイライラしない方法を知り、相談できる相手を見つけておくのも重要です。
今は睡眠不足で大変な時期でしょう。しかし、朝までぐっすり幸せそうに寝ている子どもを見る日は、きっとやってきますよ。

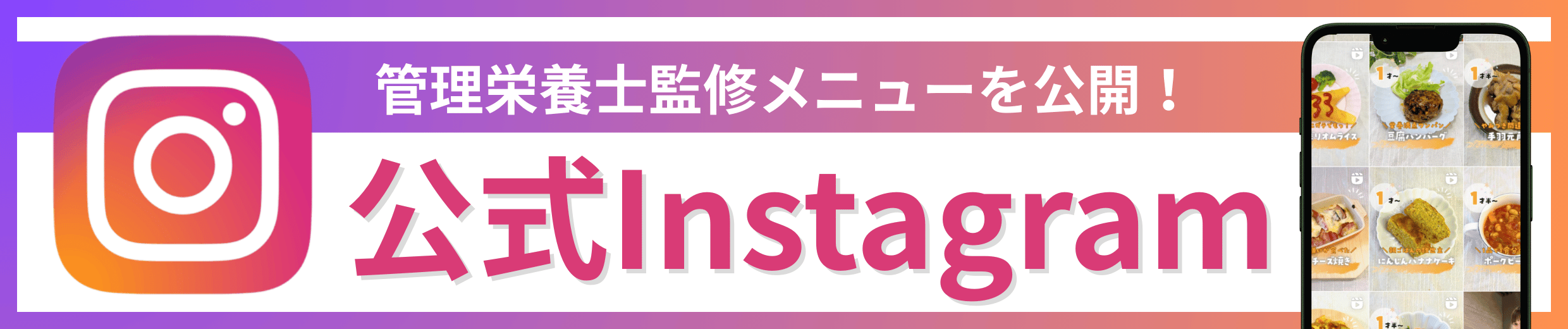


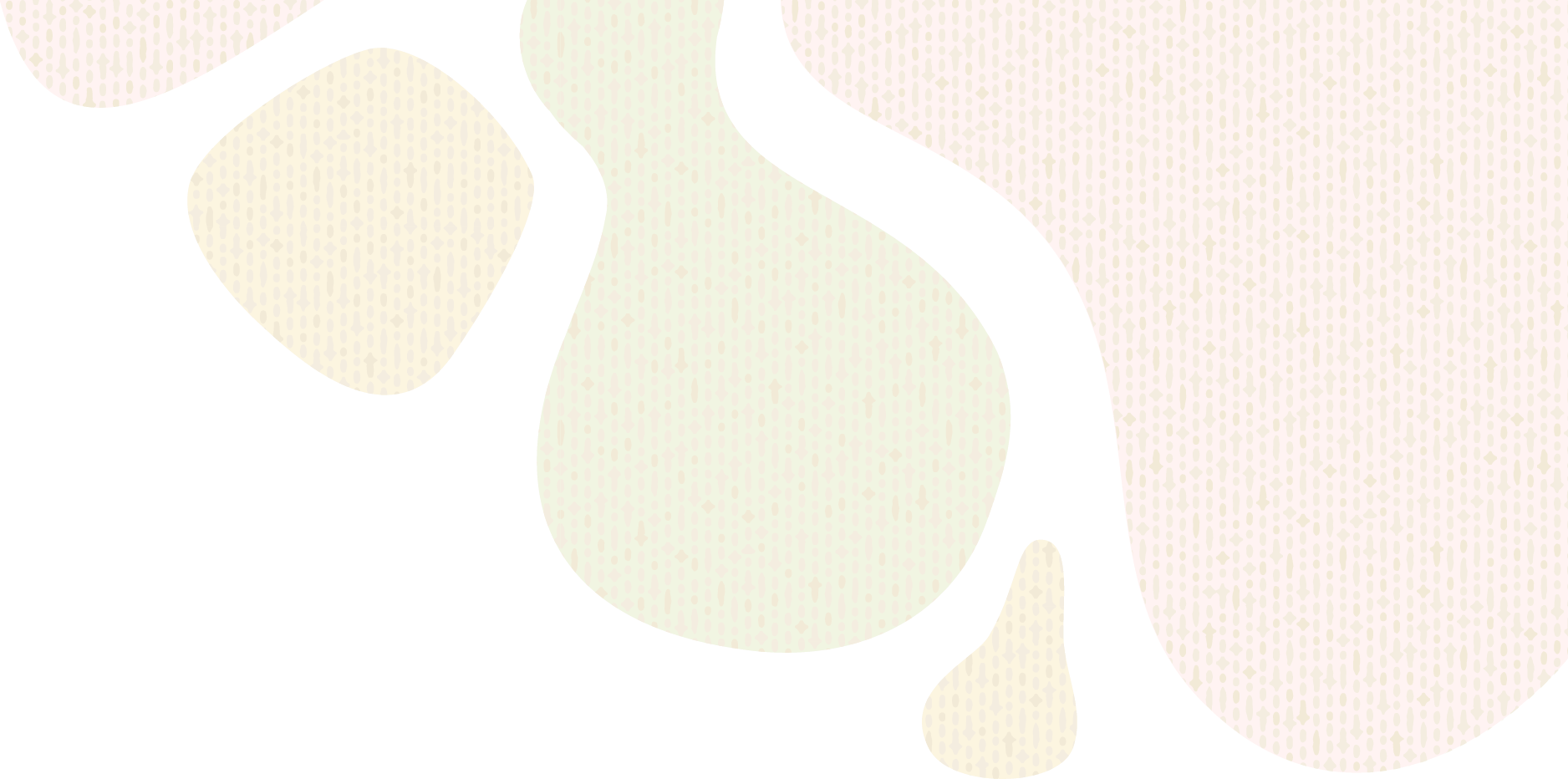










 にこにこ鉄分特設サイト
にこにこ鉄分特設サイト





