【PR】
子供の栄養不足が問題になっている
身長や体重、臓器などの成長が著しい子供では、食事からさまざまな栄養素を補う必要があります。
しかし好き嫌いや偏食などの食に関する悩みも多くなる時期でもあるため、ママやパパは不安になってしまいますよね。
子供の栄養不足の原因や新型栄養失調を知って、成長のために必要な栄養素を毎日の食事で補いましょう。
子供の栄養不足の原因
子供の栄養不足の原因には、さまざまな要因が考えられます。特に自我が芽生える乳幼児期では、好き嫌いや特定の食べ物しか食べないといった偏食、少食やアレルギーの有無によって、かたよった食事になりやすい時期でもあります。
栄養不足にならないように、子供の成長に必要な栄養素を毎日の食事から補いましょう。
「新型栄養失調」とは
新型栄養失調とは1日に必要な摂取カロリーは補えているものの、特定の栄養成分が不足している状態のことをいいます。
好き嫌いや偏食、少食などの食に関する問題が多い子供では、新型栄養失調のリスクが高まってしまいます。
ビタミンやミネラル、食物繊維などの不足しやすい栄養素を意識して食事から摂取しましょう。
子供の成長に必要な栄養素
子供の成長には炭水化物、タンパク質、脂質などの三大栄養素に加えて、さまざまな栄養素を補う必要があります。
三大栄養素以外にも意識して補いたい子供の成長に必要な栄養素を解説するので、参考にして毎日の料理で取り入れてみてくださいね。
鉄分
鉄分は赤血球を作るのに必要な栄養素で、子供の健康な成長のためには欠かせない栄養素です。
肉類や魚介類、野菜類に多く含まれている栄養素ですが、噛みにくかったりパサパサしていたりすることが原因で子供が避けやすい食材でもあります。
生後6カ月以降になると、胎児の間にママからもらった鉄分が少なくなっていってしまうため、鉄欠乏にならないように食事から意識して鉄分を補いましょう。
カルシウム
カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です。
乳幼児期の食事からのカルシウム摂取量は、大人の2/3程度が推奨されています。
カルシウムが豊富な食べ物は飲み物やおやつとして取り入れる方法もよいでしょう。
ビタミンDやビタミンKなど、カルシウムの吸収を助ける栄養素と一緒に摂取するのがおすすめです。
ビタミン
ビタミンには大きく分けて水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンがあります。
ビタミンAやビタミンD、ビタミンB1などのビタミンは種類が多く、それぞれはたらきも違っています。
いろんな食べ物に含まれている栄養素ですが、かたよった食事が続いていると不足しやすくなってしまうため注意が必要です。
タンパク質
筋肉や臓器など、からだの構成成分でもあるタンパク質。
タンパク質は子供の成長に欠かせない栄養素のうちのひとつで、肉類や魚介類、卵や豆類、乳製品などに多く含まれています。
体重や体格から比較すると、成長期の子供では大人よりも多くのタンパク質を補う必要があるので積極的に摂取しましょう。
栄養素を効率よく摂取するためのポイント
子供が栄養不足にならないためにも、成長に必要な栄養素を効率よく摂取することが大切です。
鉄分やカルシウム、ビタミンやタンパク質などの子供が積極的に補いたい栄養素を効率よく摂取する方法をご紹介します。
魚を料理に取り入れる
魚には鉄分やカルシウム、ビタミンやタンパク質などの成長に必要な栄養素が豊富に含まれています。
また魚には、子供の考える力をサポートするDHAなどの栄養素も多く含まれています。
栄養不足が気になる時や子供の考える力を育みたい場合には、普段の料理で魚を積極的に取り入れましょう。
サプリメントを使う
特定の食べ物しか食べない場合や魚をあまり食べてくれない場合には、サプリメントを取り入れてみるのもよいでしょう。
子供用のサプリメントには粉末タイプやチュアブルタイプ、グミタイプなど、さまざまな形状のものが販売されています。
子供用サプリメントを使う場合は対象年齢が合っているもので、鉄分やカルシウム、ビタミンやタンパク質が補える商品を探してみてください。
子どもに必要な栄養素を補える にこにこ鉄分
子供の成長に欠かせない栄養素を毎日料理から補おうと思うと大変ですよね。
子供の成長に必要な栄養素を手軽に補いたい方には「にこにこ鉄分」がおすすめです。
にこにこ鉄分は、鉄分やカルシウム、ビタミンやタンパク質などの栄養素をまとめて補える粉末タイプのサプリメントです。
生後6カ月以降の赤ちゃんから使えるので、偏食や少食などがあって子供の栄養不足が気になる場合はぜひ試してみてくださいね。
おわりに
乳幼児期の子供に多い偏食や好き嫌い、少食などの食に関する悩み。
特定の食べ物しか食べないと、新型栄養失調などの栄養不足のリスクが高まってしまう恐れもあります。
栄養不足にならないためにも、子供の成長に必要な栄養素を知って毎日の食事で意識して取り入れてみてくださいね。
ライタープロフィール
谷岡 友梨
保育園の管理栄養士として働きながら、ママやパパからの離乳食相談や離乳食や幼児食のレシピ考案にも携わっている。
1児の娘の母として仕事と育児の両立に奮闘中。
よくある質問
Q:子どもが鉄分不足になると、どんな症状がありますか?
貧血(顔色が悪い、疲れやすい)、集中力低下、食欲不振、イライラしやすいなどの症状が出ることがあります。
Q:子どもに必要な鉄分の摂取量はどれくらいですか?
1~2歳で約4.5mg、3~5歳で約5.5mgが目安です。食事からの摂取が基本です。
Q:鉄分を多く含む食材には何がありますか?
レバー、赤身肉、しらす、かつお、ほうれん草、小松菜、大豆製品などが挙げられます。
Q:子どもが鉄分の多い食材を嫌がる場合、どうしたらいいですか?
ハンバーグやお好み焼きに混ぜたり、スープにするなど調理を工夫するのがおすすめです。
Q:鉄分のサプリメントは子どもに飲ませても大丈夫ですか?
1日の推奨量の範囲内であれば問題ありません。にこにこ鉄分は1日1包、親子で利用することが可能です。

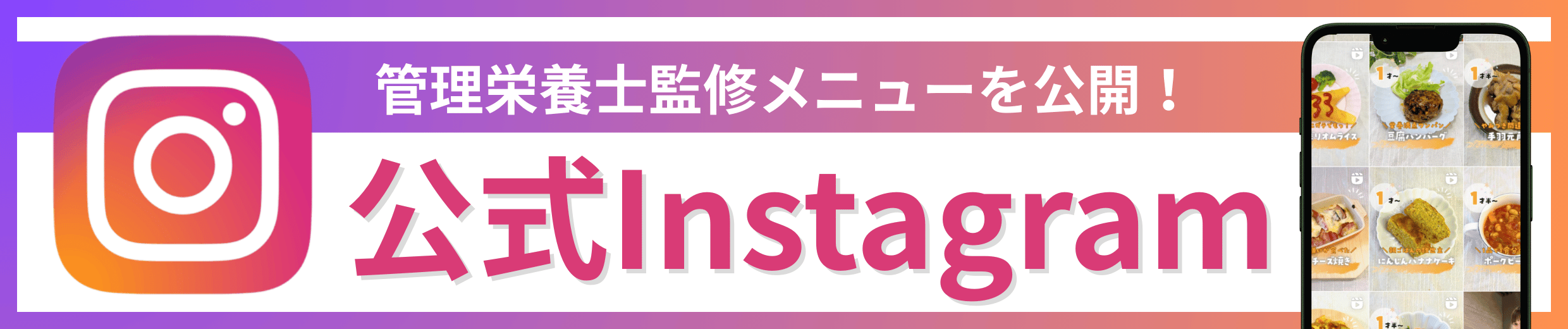


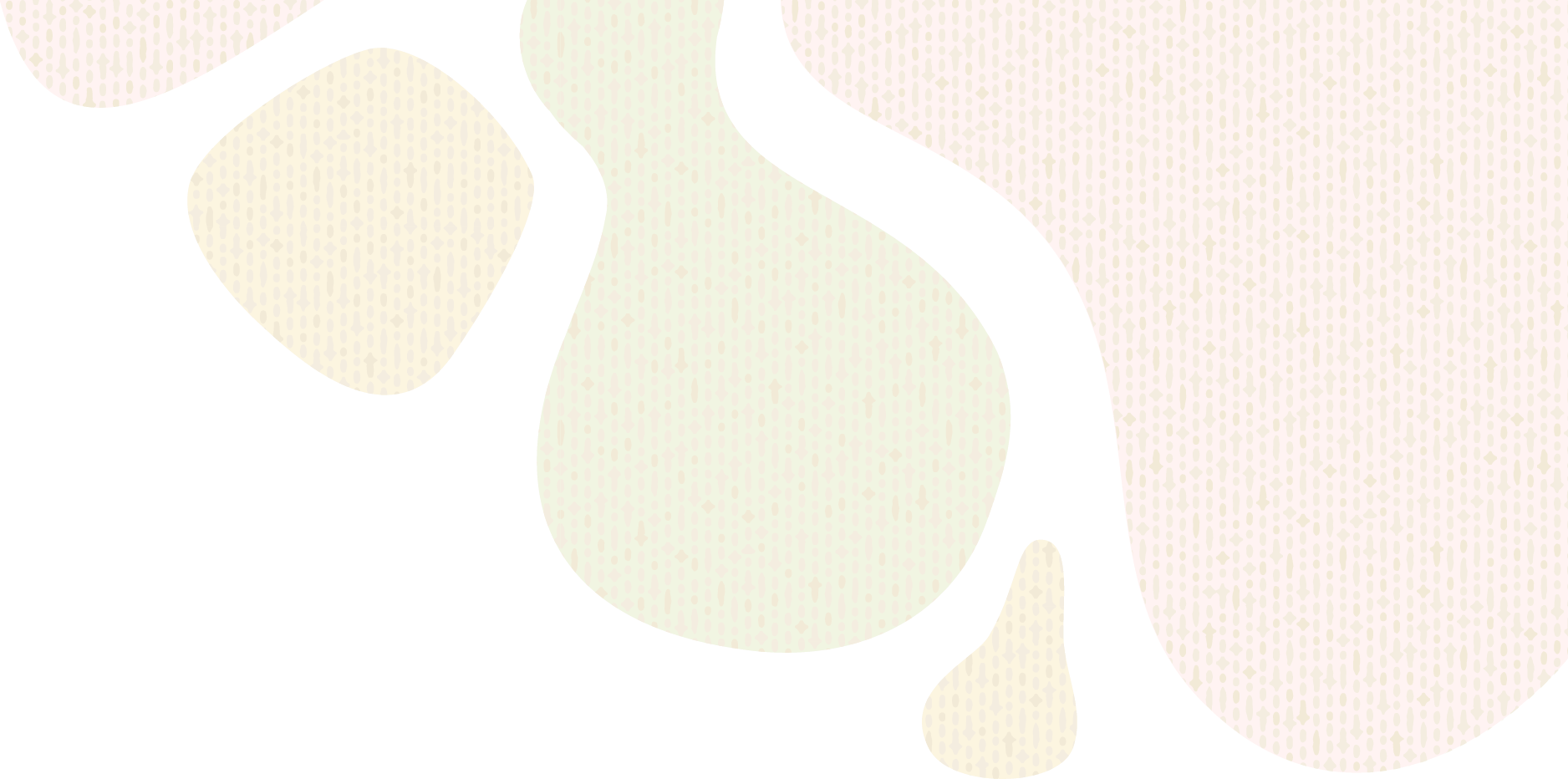











 YORISOU SHOP
YORISOU SHOP にこにこ鉄分特設サイト
にこにこ鉄分特設サイト





